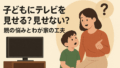【導入】
小学校の入学を機に、子どもに関する「細かいけど忘れたくないタスク」が一気に増えました。持ち物の準備、学校行事の予定、プリント類の提出期限など、どれも些細だけど忘れると影響が大きい。頭の中では常に「アレもしなきゃ」「コレもまだ」と考え続けていて、正直疲弊していました。
「ちゃんと覚えておかないと」と意識すればするほど、心のゆとりがなくなる…。そんなときに出会ったのが「GTD(Getting Things Done)」というタスク管理の考え方です。
GTDとは?
「GTD(Getting Things Done)」とは、デビッド・アレン氏が提唱したタスク管理の手法で、「頭の中の気になることをすべて書き出してシステマチックに整理することで、ストレスなく生産性を向上させる」ことを目的としています。
GTDの基本プロセスは以下の5つのステップで構成されます。
1. 収集(Capture):気になることをすべて外部のツール(メモ、アプリなど)に書き出す。
2. 処理(Clarify):タスクとして実行可能か判断し、適切な処理方法を決める。
3. 整理(Organize):プロジェクトや次のアクション、リマインダーなどに分類して管理する。
4. 見直し(Reflect):定期的にリストを見直し、状況の変化に応じて更新する。
5. 実行(Engage):適切なタイミングでタスクをこなす。
GTDに出会って変わったこと
「とにかく全部書き出す」だけで頭が軽くなる
GTDの基本は、「頭の中の気になることをすべて外に出す」こと。子ども関連のタスクも例外ではなく、「給食袋を洗う」「予備のハンカチを確認する」「学校のアプリの通知をチェックする」など、細かいことほど書き出して可視化します。
このときに優先度や重要性などをまったく考慮しないのもGTDの特徴です。大小問わず頭の中にあって気になるタスクは出し切るようにしましょう。
「ああ、そういえば○○しなきゃいけなかったんだ」とか「○○しないとなぁ」などと頭の中でぐるぐると考えているのって、実はかなり脳のエネルギーを消費しています。いったん書き出してしまえば、脳の”メモリ”が開放されて、他のことに集中できるようになるのです。
どこに書き出すか?私の実践ツール例
私はアナログ派なので、バレットジャーナルの手帳を使っていますが、付箋やホワイトボード、スマホのメモアプリなど、書き出せるなら何でもOKです。
私の習慣は「朝の10分」。その日の頭の中のもやもやを全部リストに出してみます。それだけで心が整い、1日のスタートがぐっとスムーズになります。
子育てタスクが“プロジェクト”化しやすい理由
「遠足準備」や「学校行事の申込」は1つのタスクじゃない!
一見1つのタスクに見えても、実は複数のステップが含まれているのが子育てタスクの特徴です。たとえば「遠足準備」には、
- レインコートの確認
- お菓子の買い出し
- 持ち物チェックリストの印刷
- 子どもへの声かけ など、さまざまな行動が含まれます。
GTDでは、これらはすべて「プロジェクト」として扱い、管理します。
「次にとるべき具体的な1歩」を明確にしておく
「遠足準備」というざっくりしたタスクのままでは、動きにくく、後回しにしがちです。
でも「レインコートが家にあるか確認する」といった具体的な一歩に分解すれば、スキマ時間でさっと取り組めます。「次にやること」が明確だと、行動へのハードルがぐんと下がります。
親の自己管理こそ、子どもの安心につながる
「忙しさに追われる親」より「整っている親」でいたい
親がタスクに追われてバタバタしていると、子どもにもその焦りや緊張感が伝わってしまいます。逆に、ある程度タスクを見える化し、整えて行動できていると、親自身の気持ちに余裕ができ、それが子どもにも安心感として伝わります。
私はまだまだ理想には程遠いですが、「忘れない仕組みをつくる」ことで、無駄に怒ることやイライラすることが少なくなった気がします。
【まとめ】
「やることが多すぎる!」と感じたら、それは頭の中に溜め込みすぎているサインかもしれません。
GTDの「頭の外に出す」習慣は、忙しい子育て中の親にとってこそ、効果的な方法です。
書き出す → 整理する → 小さな1歩に分解する。
たったこれだけで、毎日の暮らしが驚くほどスムーズに、そして心も軽くなるはずです。